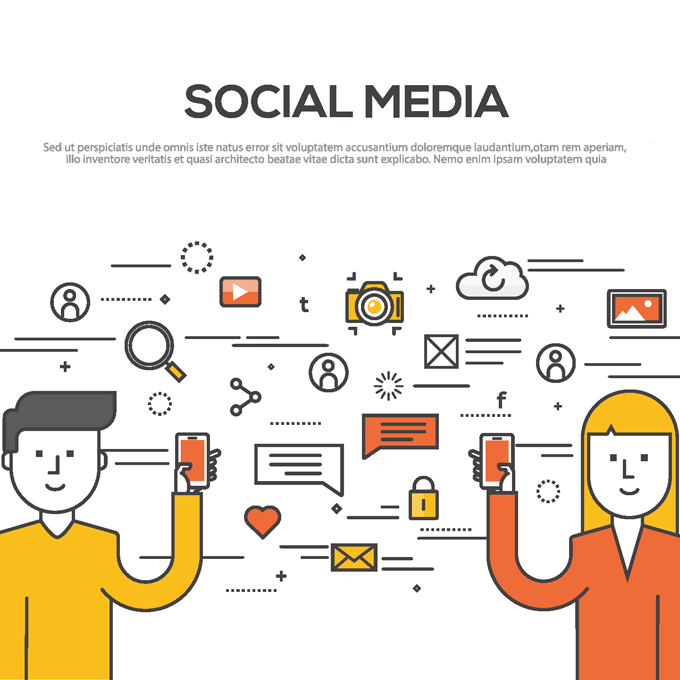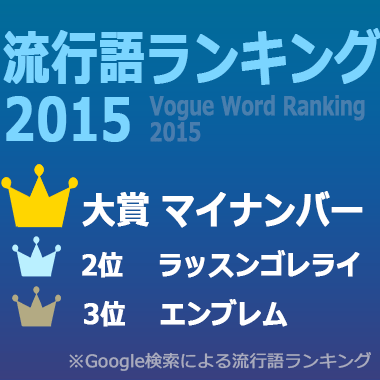このメディアでも繰り返し書いていますが、フジロックファンであるところのエモジマの夏は7月末を持ちまして終了いたしました。
いやむしろ、これから12ヶ月後のフジロックに向けて、1年がスタートすると言っても差し支えない…みなさん、明けましておめでとう。
さて、お祭りの後は振り返りが大切。ただのお客さんであれば「あー楽しかった」で終われるのですが、主催側は大反省会をしていることでしょう。
「あー楽しかった」で終わっている僕らを来年も「また行きたい!」と思わせるように、あーでもない、こーでもないと振り返っているはず。
僕らの本業であるデジタルマーケティングでも同じことが言えます。
施策を打ったら振り返り。データを見ては、仮説を立てて、また検証といった具合に。
ただ、「あのデータ取れてなくない?」など、レポートを作る際に不備に気付いて後の祭りという経験がある方は多いのではないでしょうか?
リリース前にレポーティングの骨組みを作る
例えば、あなたがとあるキャンペーンサイトを制作、運用して、レポーティングをしなければならないディレクターだとしましょう。
あなたはキャンペーンサイトを企画して、最終的に成果を証明して上司に報告しなければいけません。
自分の成果を証明するため、まず材料となるデータを集めなくてはなりません。正しくデータを計測して、初めて筋道立てたレポーティングができるのです。
注意しなければいけないことは、Web上のデータというのは後から取るのが難しい点です。サイトをオープンしてしまった後からデータの計測を開始しても、それまでのデータを遡って取得はできません。
キャンペーン開始前からレポートのアウトプットイメージを明確にし、そのために必要なデータをしっかり取得できるよう設定しておく必要があります。
入口から成果地点までをトラッキング
ではどういったデータが必要になってくるのでしょうか?
まず、キャンペーン企画のコンセプトを決めて、内容をまとめます。その際に、ユーザーに求める行動、到達地点が見えてくるでしょう。「商品を購入する」「プレゼントに応募する」「資料をダウンロードする」など具体的な行動であることが多いです。
次にコンセプトと目的を元に、キャンペーンサイト内の中身を作ります。ユーザーがどこを見て、どこをクリックして、最終的な到達地点に辿り着くのかという導線を設計します。
また同時に、どのような方法で人を呼び込むかも検討します。広告出稿なのか、ソーシャルメディアなのか、メルマガ告知なのか、はたまたフィジカルなチラシなのか。このキャンペーンへの入口を検討します。
レポーティングの基礎は、
・どれだけ成果が出たか(購入者数、応募数など)
・成果が出た入口はどこか(流入経路)
・成果に至らなかった人はどこで離脱したのか(導線分析)
の3点を抑えましょう。
ユーザーがどの入口から入ってきて、どの道を通ってゴールに到達したかをトラッキングすることがサイト分析の基本となることが多いです。
実際には逆方向から分析することが多く、ゴールに到達した人がどの入口を通って来たかを把握することで、どの集客施策が1番効果があったかを評価することができます。
また、集客はあるのに応募数が少ないといった場合には、サイトの導線上のどこで離脱しているのかを辿ることで、課題を洗い出すことが可能です。応募フォームでの離脱率が高ければ、入力項目のハードルが高いなどの仮説を立てることができます。
それぞれの正確なデータ取得設定をしておく
「入口」「導線」「成果地点」の正しいデータ取得をリリース前に必ず設定しておきましょう。それぞれの地点でデータの取得方法が違ってきます。(今回の記事は、Google Analyticsを活用する前提です。)
入口(流入元)
まず入口となる流入の参照元をトラッキングします。
参照元にはいくつか種類があり「検索流入」「リファラー(被リンク)」「ダイレクト」「ソーシャル」「その他」などがあります。注意しなくてはいけないのは、「その他」の部分です。
「その他」には「広告」「メルマガ」「チラシからのQRコード」などが含まれ、どこから流入したのかをGoogle Analyticsで認識できるように定義する必要があります。その際に使われるのがUTMタグです。
http://www.example.com/?utm_source=”参照元”&utm_medium=”メディア”&utm_campaign=”キャンペーン名”
URLに”?”をつけてパラメーターを付与することで、どのメディアに出している広告か?どのキャンペーンなのか?を定義することができます。
ユーザーがこのリンクをクリックすると、自動的にGoogle Analyticsで計測という仕組みです。
導線
導線の分析に方法は様々ありますが、基本的にはデフォルトのGoogle Analyticsの設定で事足りることが多いです。
成果地点に至るまでに、
トップページ → 商品詳細ページ → カート → 決済入力フォーム → 完了ページ
など経由する最中、どこで人が離脱しているかなどを分析します。それぞれのページビューはデフォルトで計測されているので特別な設定は必要ありません。
もしサイト内で「特定のバナーをクリック」、「特定のリンクをクリック」などのイベントを計測したい場合は別途タグを設定する必要があります。タグマネージャーなどのツールを勉強しておくと非常に効率的にタグの設置が可能です。
※参考記事:Google Tag Managerでリンクのクリック数をカウントしてみよう!
成果地点
最後に、キャンペーンの結果どのくらいの成果が出たかを見えるようにしましょう。そのキャンペーンの内容によりますが、商品購入や応募などの成果地点に何人到達したかを計測します。
設定の方法は簡単で、Google Analyticsで目標を設定するだけです。商品購入ページや応募完了ページなどのURLを指定し、そのページに到達した人数をカウントします。資料のダウンロードなどを成果地点としている場合は、ダウンロードのイベントを計測し目標として設定します。
まとめ
キャンペーンを通して、どのくらい成果があったのか、何が良かったのか、何が悪かったのかを判定するには、判断するためのデータが絶対に必要になります。
正しい計測設定ができていないことがキャンペーン開始後に判明しては遅いので、事前にテストを繰り返し万全の準備をしておきましょう。
ウフルではキャンペーンの企画から制作、レポーティングまでをワンストップで支援しています。今回は詳しい設定方法までお話することができませんでしたが、もっと詳しく知りたい、協力して欲しいといった場合には、ぜひお気軽にご相談ください!
さて、フジロックまで後353日…なんてうつつを抜かしている前に仕事しまーす笑

エモジマ
最新記事 by エモジマ (全て見る)
- そのマーケティング、偏りすぎてない?トリプルメディアの特徴を理解しよう - 2018年3月22日
- SNSの反響は4年で20倍!ブラックフライデーは日本でも定着するのか? - 2017年11月30日
- コンテンツマーケティングで押さえておきたい重要な4つのスキル - 2017年10月20日